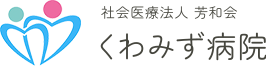内科外来
| 概要紹介 |
当院は内科外来として、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、漢方内科、糖尿病外来の診療を行っております。内科の各分野における初期診療と慢性期のマネジメントに力をいれています。専門的な治療を要する場合には、適切な医療機関にご紹介いたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療内容・担当医師 |
● 呼吸器内科あらゆる呼吸器疾患が対象ですが、気管支喘息やCOPD、咳喘息をはじめとする慢性咳嗽(長引く咳)、肺炎や気管支拡張症、間質性肺炎や呼吸不全、睡眠時無呼吸症候群などに力を入れています。 <診療体制>
※ 第1(土)呼吸器のみ、第2・3・4は睡眠外来 <担当医師>池上あずさ(日本睡眠学会指導医・総合専門医、日本プライマリ・ケア学会認定医) 福原 明(日本睡眠学会指導医・総合専門医、総合診療指導医・専門医) 高城 愛子(日本内科学会総合内科指導医・専門医・認定内科医)
● 循環器内科虚血性心疾患、不整脈、弁膜症、心筋症などに対応しております。手術等の適応となる大動脈瘤、大動脈解離については他の医療機関と連携して治療を行います。 <診療体制>
※ 第2・4(土)のみ <担当医師>
赤木 正彦(日本プライマリ・ケア連合学会認定医) ● 漢方内科現代医学的な診断を行った上で、漢方薬を中心とした内科治療を行っております。病気や症状だけでなく、悩みを抱えている人の背景にある体質や性格など、一人ひとりの特性をふまえた診察・治療を行っています。西洋薬との併用も可能です。 <診療体制>
<担当医師>
成田 文親 他 ※ 診療技術員として中医師(王暁東中医師)が同席します。 ● 糖尿病外来代謝疾患(糖尿病、脂質異常症、肥満症、高血圧症、高尿酸血症など)を広く診療していますが、特に糖尿病は診療の中心となっています。食事・運動療法を重視し、必要最小限の薬による良いコントロールに努めています。血糖を下げるだけでなく、糖尿病にまつわる合併症を予防することを目標にしています。 <診療体制>
<担当医師>すべての内科医師 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予約方法 |
お電話にてご予約をお願いいたします。 予約受付時間9:00~16:45 |